パーカッションで、コンガ、ジャンベ、ボンゴ・・・打面(ヘッド)が皮の楽器を初めて持ったとき、これって何かお手入れ必要なのかな?皮だから何か注意しないといけないのかな?と、気になることはありませんか。
私はあまり気にしないで使っていて、不注意から楽器を汚損したことや、破損したことがあります。その経験から、皮の楽器の取り扱いで注意すべき点をまとめてみました。
破損したらヘッド張り替えないといけなくなることもあります。
そうなるとお金もかかるし、その間楽器が使えないのも困りますね。
大切な楽器をダメにしないために知っておいた方がいいことと、私の失敗談も参考にのせました。
ぜひ最後までご覧ください。
皮のヘッドの損傷パターンは2種類
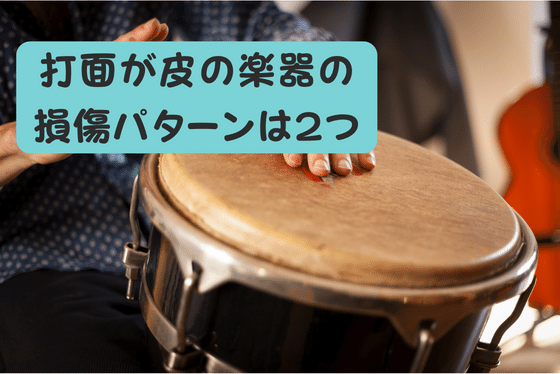
コンガ、ボンゴ、ジャンベなど、ヘッドが皮の楽器の損傷は、大きく分けると次の2パターンです。
- 皮にカビが生える
- 皮が破ける
私は両方経験ありです”(-“”-)”
順にみていきましょう。
皮にカビが生える
日本ではバッグや靴など皮の製品を、しばらくしまったままにしていてカビが生えてる!と驚くことがありますよね。ヘッドが皮の楽器も同じです。
楽器も頻繁に使っている場合はそんなにカビが生えることはないように思いますが、少し使わずにいると、気づいたときにはカビが生えていた!ということも。
汚れているとさらにカビは生えやすいようです。

私はパンデイロをケースに入れて年レベルで放置していて、ある日取り出してみたらヘッドがカビだらけになっていました。
皮が破ける
皮は湿度が高いと伸び、乾燥すると縮みます。このため、乾燥して急激に縮んだとき、皮が強く引っ張られ場合によっては破けます。
例えば、
- 夏に気温が急に高くなった時、ヘッドが一気に乾燥して破ける。
- 冬に乾燥して破ける
傷やカビなどがあるとそこから破けやすくなり、その場合は大きな収縮でなくても破けることもあるようです。

私はボンゴを長期間使わなかったとき、知らないうちにヘッドのテンションがあがっていて、ある日「パーン!」と破裂音がして、見に行ったらヘッドが裂けていました。
楽器を守るための対策

では、大事な楽器を守るためにはどうしたらいいでしょうか。
ここではそれぞれの予防方法・対策をまとめました。
カビの予防策
カビの予防策は主に次の3つです。
- 湿気を避け、できるだけ風通しの良いところで保管する
- 水にぬらさない
- 汚れたままにしない
具体的には次のような感じになります。
風通しの良いところで保管する
- 出来るだけ乾燥した風通しの良い場所で保管する。
楽器を、締め切った普段使っていない部屋に置きっぱなしにしない
エアコンをつけている部屋なら安心ですが、エアコンの風が直接当たる場所は避けます。
日本の梅雨時に完璧な方法はないと思います。出来る範囲で予防するしかなさそうです。 - ケースに入れっぱなしにしておくとカビが生えやすい。
ケースは運搬のために使い、保管するときはケースから出して風通しの良いところに置く。
濡らさない
雨の日に楽器を運搬するときは、可能な限り濡らさないように注意します。
見た目は悪いですが、90Lの大きなゴミ袋を利用すると、大きな楽器も覆うことができます。私は、楽器をゴミ袋に入れて、それをケースに入れた後、さらにゴミ袋で覆って運搬していました。見た目よりも、楽器を守ることが大事!
雨が降りそうなときは、いつでも守れるようにゴミ袋を持ち歩いていました・・・
汚れたままにしない
汚れがついているとカビが生えやすいです。
コンガ、ジャンベなど、どれも手で叩く楽器なので、使っていると自然と汚れます。
時々柔らかい布や、皮専用のクリーナーでふき取るといいようです。
皮のヘッドが破けないようにする予防策
皮のヘッドが破けるのを予防する方法としては、大きく分けて次の3つがあげられます。
- 温度・湿度の急激な変化をできるだけ避ける
- 使わないときは皮にテンションがかかりすぎないように緩めておく
- カビや傷がつかないように注意する
具体的には下記のような対処法が考えられます。
- 楽器は温度、湿度が大きく変動しない場所で保管する。例えば、直射日光がさす場所、エアコンの風が直接あたる場所は避けるなど。
- 車に積みっぱなしはNG
- 使い終わったらヘッドの張りを緩める。
そんなにテンションをかけない場合はよいのですが、ピッチを高めにチューニングする太鼓は特に気をつけた方がいいです。

私も以前は「そんなに神経質にならなくてもいいんじゃね?」と、ヘッドを緩めたりしていませんでしたが、ボンゴのヘッドが破けてからは、気をつけるようになりました。
- テンションを上げて叩くコンガのキントは、使い終わったらヘッドを緩める
- 梅雨が終わって気温が急に上がる頃や、急に気温が下がる冬の初めは、急激に乾燥するのでこまめに太鼓をポンポンと叩いて回って、音が上がっていたら緩める。
(ほんとにある日急に上がりますよ!)
そんなにテンションかけない低音の太鼓はそこまでこまめにしていません。
また、破けたボンゴのヘッドは皮ではなくファイバースキンにしたので、特に緩めたりしていません。
- カビがつかないように気をつける。
梅雨明けに温度が上がり乾燥して、そこから破けることがあるそうです。 - 時々オイルを塗ってメンテナンスする。人の肌と一緒で、乾燥するとカピカピになってそこからひび割れてくるそうですよ。

私は時々ハンドクリームを塗っています。
複数の先生が、自分の手にハンドクリームをつけたついでに、「楽器にもつけておこう」と言って、皮の打面にもハンドクリームを塗っているのを見たので、みんなやっているんだなぁと思いました。
私の失敗
上でも書いた私の過去の失敗談について、もう少し具体的にご紹介します。
悪い例としてご覧ください・・・(;^ω^)
パンデイロにカビが生えた
パンデイロをケースに長期間入れっぱなしにして、ヘッドにカビが大量発生した話です。

3~4年放置してました・・・
慌ててアルコールや洗剤をつけた布で拭いたけど全然取れず、最終的には水で薄めた漂白剤をヘッドがびしょびしょになるまでスプレーしました!
ヘッドがダメになるかなと思いましたが、カビは一応取れて、室内で乾燥させたらまた使えるようになりました。(おすすめはしません)

大体きれいになった

よく見ると黒いカビの後が残っています。
これ以来、楽器を保管するときは必ずケースから出すことにしました。
今はこんな感じに、タンバリンと一緒に書類立てに並べて保管してます。

ボンゴのヘッドが破けた
ボンゴの小さいほうのヘッドが破けました。

見えにくいけど、矢印の先のところが裂けてます・・・
これは引っ越して保存場所の環境が変わった直後に起こりました。
引っ越し前の保管状況が悪くて湿度が高かったのだと思います。
引っ越してしばらくたったある日、「パーン!!!」と音がして皮が破けました。
音がしたとき、何か金属が倒れたのかと思って見に行ったけど、最初何の音かわかりませんでした。
そしてあとから、ボンゴの皮が破けているのを発見して、あの音はこれか!と思いました。

季節は秋で、そんなに乾燥する時期ではありませんでした。ヘッドが破けた原因は以下の通りだと思います。
- 引っ越して環境が変わった(たぶん湿度が変化した)
- しばらく使っていなかったのに、ヘッドの張りを緩めていなかった。
湿度が変化するのはある程度避けられないですから、やはり使わないときに緩めておくことは大切だと身をもって知りました。
まとめ
- コンガ、ジャンベなどの楽器でヘッドが皮の場合、起こりうる事故としては、主にカビが生える、と皮が破けるがあります。
- カビの予防には、①風通しの良い場所に保存する、②濡らさない、③汚れたままにしない
- 打面の皮が破けるのを予防するには、①温湿度の急激な変化を出来るだけ避ける、②皮が張りすぎないように気をつける、長期間使わないときは張りを緩める、③カビや傷がつかないように注意する
最後までご覧いただきありがとうございました。


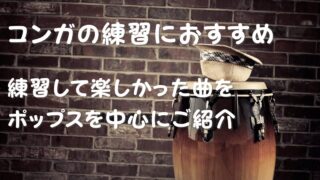

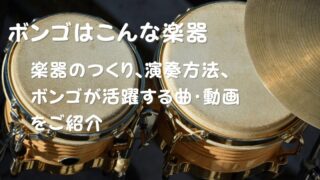
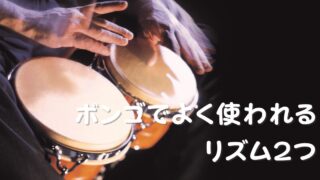
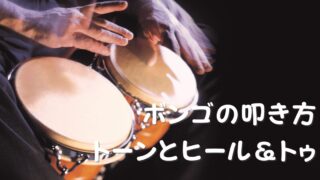
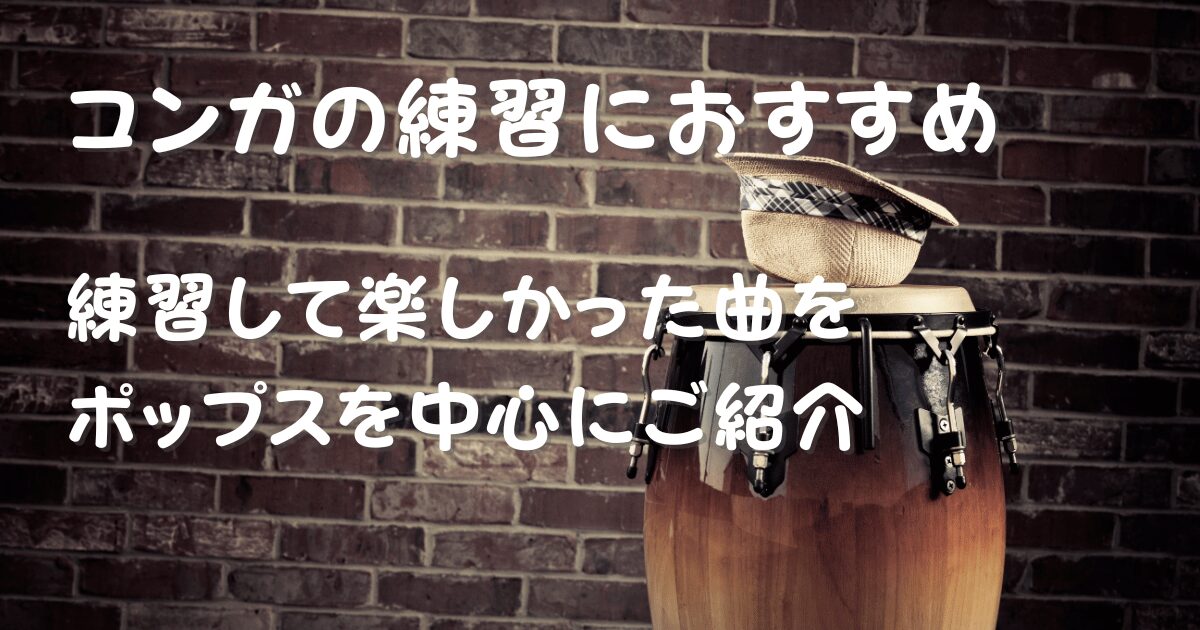

コメント