パーカッションをやっていると言うと、よく「すごいね~!私はリズム感ないから無理だわ」と、お約束のように返されます。
でも、それは本当でしょうか?
大人になってから楽器を始めたいけど「リズム感がない」と心配する声もよく聞きます。
でも、リズム感は“天性の才能”だけで決まるものではなく、大人になってからでも鍛えられるものだと思います!
実際、音楽をやっている人の多くが「リズム感がない人はいない」「練習で鍛えられる」と言っています。
私自身も、大人になってパーカッションを始めてから、練習によってリズム感が磨かれていると感じています。
この記事では、大人になってからパーカッションを始めた私が感じた
- リズム感のある人とない人の違い
- リズム感のない人はほとんどいないということ
- 大人でもリズム感を鍛えられる
- 実際にできる練習方法
についてまとめました。
「リズム感は生まれつきじゃないの?」「音楽を始めたいけど自信がない…」という方に、一歩を踏み出す参考にしていただけると嬉しいです。
リズム感とは?

リズム感とは、音楽のテンポや拍子などを感じ、それに合わせて身体を動かしたり、音を出したりする能力を言います。
歌や楽器の演奏、ダンスをする上で大切な感覚です。
テンポが合っているだけではなく、ビートや細かなリズムをうまくとらえてそれに合った表現ができることが、リズム感があると感じられるポイントだと思います。
リズム感のある人とない人の違い

リズム感がいい人、悪い人
リズム感のある人は、音楽にピッタリ合った表現ができて、聴いていても心地よいですね。
そういう人は、例えばメトロノームや音楽にぴったり合ったリズムが刻めるほかに、簡単に裏拍が叩けたり、3拍子系のリズムがすぐにとれたり、またドラムの鳴っていない曲でも、簡単にリズムを合わせることができます。
逆に、リズム感がない人は、演奏やダンスの動きが音楽とずれている、テンポが一定しない、他の楽器とタイミングを合わせられないなどのような感じではないでしょうか。
ではリズム感がある、ないというのはどのように決まるのでしょうか。
リズム感は生まれつきだけでは決まらない
やはり、生まれつきリズム感のいい人はいるように思います。
それは、生まれつき運動神経のいい人がいるのと同じです。
でも、リズム感は持って生まれた才能だけで決まるのではなく、環境や本人の努力といった後天的なものの影響が大きいのです。
例えば、もともとリズム感がよい子どもなら、その子は音楽を聴く時、リズムに注目して聴くでしょう。
つまり、自らすすんでリズム感を鍛えている状態です。
そうして自然にリズム感はどんどん磨かれていくから、結果的に生まれつきリズム感がいいようにみえるかもしれません。
でも実際は、才能以外の努力や習慣の影響が大きいのです。
脳科学でも「興味のある情報は加工が深くなり、神経回路が強化される」と言われているようです。
リズム感が特にいいというわけではない人の場合は、そのままだと音楽の中のリズムを何となく聴いているかもしれません。それだと、リズム感は鍛えられないですよね。
ですから、リズムとはどういうものか?どうとらえるといいのかを知って、音楽の中のリズムに注目する方法がわかれば、リズム感を鍛えていけるはずです。
それにはちょっとした理解と練習の習慣が必要ですが、興味があれば誰でもできるものだと思います。
リズム感のない人はほとんどいない
そもそも、リズム感がほんとになくて、鍛えてもだめな人っていないの?と思う方もいるかもしれません。
でも本当にリズム感がない人はほとんどいないそうですよ。
これについては、プロの音楽家の方の意見をご紹介します。
ベーシストで音楽プロデューサーの藤谷一郎さんは、ご自身の動画16 Bass Lessonの中で
「本当にリズム感が悪い人はいないんじゃないか。ほとんどはリズムが悪いんです。多くの人は練習で身に着けることができます」と話されています。
(Youtube動画↓)
【リズム感】リズム感のない人の特徴3選!自分にはリズム感がないんじゃないか?と思っている人は是非見てください!
リズム感が悪いとはどういうことか

では、リズム感が悪いとはどういうことか、ここではもう少し具体的に考えてみます。
私はダンスとパーカッション、ドラムをやってきて、リズム感が悪いということについて下記のように感じました。
(藤谷一郎さんの言う、リズム感が悪いのではなく、リズムが悪いというところですね)
- リズムの構造を理解していない
- 練習不足
- 耳のトレーニング不足
- 音楽を聴かずに、自分が思うリズムを聴いている
リズムの構造を理解していない
これは文章では書きにくいのですが、リズムには構造があって、それを理解せずイメージだけで考えていると正確に表現できず、リズム感が悪いという状態になってしまいます。
例えば、「タタッタ」というリズムがあったとします。
これは、音符が4つあるうちの3つめの音が無音になっている状態。
なので、「タタッタ」を「タタ(無音)タ」と理解して表現する人と、「あ、タタッタね~」と雰囲気でリズムをとらえる人とでは差があります。
リズムの構造を理解して表現するのはとても大切なのです。
練習不足・経験不足
いくらリズムの構造を理解していても、練習不足だと自分の理解通りに表現できません。
音楽を聴いてその中のリズムを聴きとること、感じた感覚に合うように表現(演奏)すること…すべてに練習が必要です。
練習不足というのは実際とても多いと自分でも感じます。
繰り返し聴いてるうちにリズムが聴こえてくることもあるし、最初は自分でも思った通りに演奏できない。
どう演奏したら感じたリズムにあうのか?というのも、練習と経験を通して身につけるものですね。
耳のトレーニング不足
最初は、リズムを聴きとる耳の能力も磨かれていません。
音楽の中のリズムを繊細に聞き取る能力もそれほどないし、自分の演奏も「音楽にちゃんとあってる」ように聴こえます。
でも練習を繰り返すうちに、前は聴こえなかったリズムが聴こえるようになるし、自分の演奏の精度も上がってきていると感じます。
また、先生に教わって耳の感覚が磨かれることもあります。
プロのミュージシャンは曲のリズムを本当に精度高く聞き取っています。
私もレッスンで、「3つ目の音が少しだけ遅れている」のように指摘されることがあります。
自分では全く気付いていなかったけど、指摘されて意識すると「確かにそうかも!」とわかるようになります。
こういう違いは、音楽聴いている人にははっきりと説明できなくても、聴いた時の心地よさなどで伝わるものだと思います。
始めた頃は、自分なりにちゃんと叩けていたつもりだったけど、少し上達すると「あれ?私の演奏、あってないな」と感じることもあるある。
これはヘタになったのではなく、耳がよくなったので、今まで気づかなかった”ずれ”に気づくようになったということです。
音楽を聴かずに、自分が思うリズムを聴いている
「リズム感が悪い」原因には、「音楽を聴いていない」というのもよく挙げられます。
そういうと、「そんなことないよ、ちゃんと聴いてるよ」と思うかもしれません。
でもこれは、曲を聴いて、「あ、この曲はこういうリズムだ」と思ったら、あとは、自分が思ったリズムを頭の中で鳴らして、それを聴いている状態だと思います。
楽器の練習をするときに音楽を聴いていないというのも、自分の頭の中のリズムに合わせて演奏して、音楽を自分の演奏に合わせて編集しながら聴いている感じだと思います。
これは実は私もやりがちで、自分では音楽をちゃんと聴いているつもりでも、こういうリズムだと思い込んでいると、曲とあっていなくても気がつかないのです。
こんな状態だと、「あれ?リズムが曲とあってないな…」と思われてしまいますよね。
大人からでもリズム感は鍛えられる

若いころならリズム感も鍛えられるかもしれないけど、大人になってからでは難しいのでは?と思う方もいるかもしれません。
でも、大人になってからでも、十分に練習で鍛えることが出来ます。
科学的にも、脳は一生変化し続ける「神経可塑性」があると言われています。
リズム感は、耳や手足だけでなく、脳のタイミングを司る回路で成り立っています。
特にリズムに関わる部分は、反復練習によってタイミングの精度が上がり、処理スピードも改善していくということです。
リズム感は、大人になってからの経験と練習で十分に育てることができます。
実際私も50歳を過ぎてからパーカッションとドラムを始めて、リズム感は鍛えられて成長していると感じるし、リズム感がよくなってくると、曲のリズムを感じて演奏することもより楽しくなります。
リズム感の鍛え方

ここでは、具体的にどのようにリズム感を鍛えたらいいか、今まで学んできた中からおすすめの方法をご紹介します。
音楽に合わせて体を動かす
例えば、下記のように音楽に合わせて体を動かします。
- 音楽に合わせて足踏みをする。スキップする。
- 足踏みをしながら手拍子をする。
- 4拍子の曲なら、足踏みをしながら1拍目だけ手拍子。
- 足踏みをしながら、1拍目と3拍目だけ手拍子。
- 足踏みをしながら、2拍目と4拍目を手拍子。
これは、私が最初にパーカッションを教わった先生が、最初のレッスンでやっていたものです。
音楽に合わせて体を動かす感覚を養うことで、リズム感が鍛えられるのですね。
私は、ダンスをしていたのでできたましたが、出来ない人は意外と多いそうです。
口でリズムを言う
演奏したいリズムを、曲やメトロノームにあわせて口で言う方法です。
例えば、「タンタタ、タタッタ、タタッタ、タタタン♪」など、そのままを口で言ってみる。
演奏するより、口で言う方が簡単にできるはずです。
逆に言えば、口で言えないリズムは演奏できません。
「なんだかうまくできない…」というときは、一旦口で言ってみると、意外と口でも言えないかもしれません。
その場合は、上で説明した”リズムの構造”が理解できていない可能性があるので、見直してみるといいかもしれません。
基礎練習、チェンジアップ
これは一番地道で確実な練習です。
どの楽器でも、初めて教わるときには基礎練習用のパターンを教わると思います。
それを、メトロノームに合わせて毎日、あるいは練習のたびに繰り返します。
3分でも5分でも、無理のなく続けられる範囲でやるのがコツだと思います。
(メトロノームはスマホの無料アプリで十分です)
カホンの基本パターンはこちらの記事で紹介しています↓
また、リズム感を鍛えるには、チェンジアップの練習もおすすめ。
チェンジアップは、一定のテンポで、「4分音符→3連→8分音符…」のように、音の細かさを変化させる練習です。
この練習は、自宅で手で机を叩くような方法でもできて続けやすいです。
打楽器では基本の練習になるので、習慣にしたいトレーニングです。
チェンジアップについては下記の記事で紹介しています↓
先生について練習する
上の章で紹介したように、自分では正しいリズムで演奏出来ているつもりでも、先生が聴くとできていないところがあることはよくあります。
高いレベルの人に教わって、指摘を受けることで自分のリズム感も少しずつ鍛えられていきます。
録音して聴いて練習する
自分の演奏をスマホで録画して確認する方法です。
これは簡単でとても効果的です。
出来てるつもりでも、録画してみると全然ずれてる💦ということもあります。
(これは先生に聞かなくても、自分でわかります。)
やはり音楽をちゃんと聴けていないということでしょうか?
客観的に見れるのでとても参考になります。
パーカッション・ドラムを学んでリズムについて感じたこと
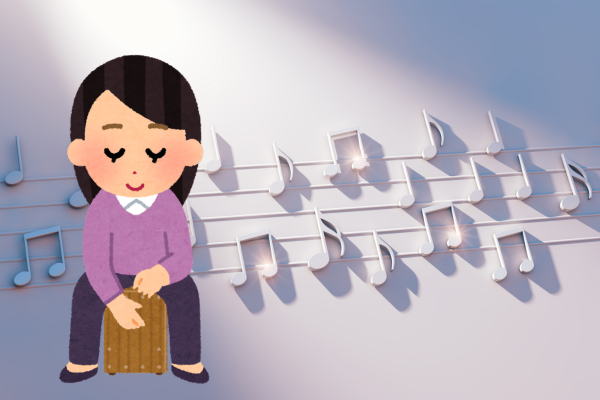
ここでは、これまでパーカッションとドラムを学んできて、リズムに関して、私が”あ、そういうことか”と感じたことをまとめてみました。
まだまだ練習中の身ですが、よかったら参考にご覧ください。
リズムは曲の流れに感覚的に合わせたほうがいい
これは音源を聴きながら練習するときですが、曲に合わせるときに拍をわかりやすく刻んでいる楽器(ドラムなど)の音から、目安になる音を一つ一つ聴いて、それに合わせて演奏しがちになります。
でも、それだと逆にぴったりにはまりにくい。
曲にもよるけど、全体のリズムの流れを聴いて、感覚的に合わせた方が”曲にぴったり”の感じになりやすいです。
感じたタイミングより早めを狙う
初心者が感じたリズムぴったりに叩くと、ドラムやパーカッションの演奏としてはタイミングが遅れている、ということになりがちかもしれません。
私は初心者のころ、感じたタイミングぴったりを狙って演奏していましたが、先生によるとそれだと遅れているとの指摘でした。
バンド演奏では、他の楽器はドラムを聴いて演奏しているので、ドラムが遅れていると、他の楽器はどんどん遅れてしまいます。
なので、思ったタイミングよりも少し早めを狙って演奏するくらいでちょうどいい。
特に私は、初心者のころピンポイントで狙いすぎていたので、叩くという動作が入ると実際に音が出るのは遅れてしまう、ということもあったと思います。
慣れると、意識しなくてもできるようにになりました。
※あくまで私の場合の話なので、そうじゃない方もいると思います。
大振りになると遅れる
大振りになるとその音が遅れます。
特に初心者のころは大振りになりがちで、レッスンではもっとコンパクトにとよく指摘されていました。
グルーブ感を生み出すことを考える
ただ正確にリズムを刻むことを考えていると、打楽器として必要なグルーブ感がなくなっていることがあります。
最終的に打楽器は、曲にあったグルーブ感を作り出し、また、他の楽器が安心して乗っかることができるベースを作ることが大切だと思います。
例えば、他の楽器の人が安心して乗っかれる低音や、見ている人に手拍子してもらえるようなトップの音(スネアの音など)を出すなどですね。
こういう表現的なところは、なかなか難しいのですが、私も少しずつ意識してリズム感を鍛えていきたいです。
まとめ
リズム感は生まれつき決まるものではなく、大人になってからも伸ばしていけるということ、また、リズム感を鍛える方法についてご紹介しました。
打楽器をやってみたいけどリズム感に不安がある方の参考になると幸いです。
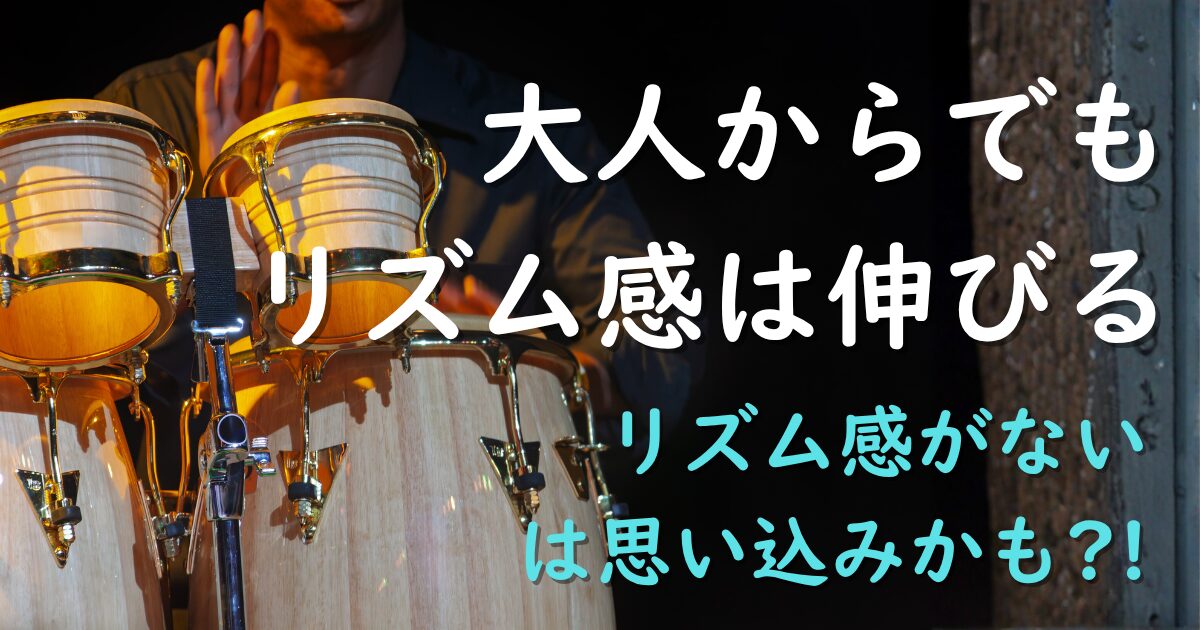
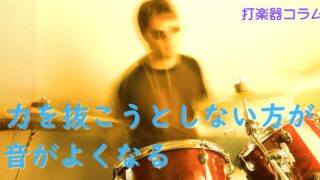
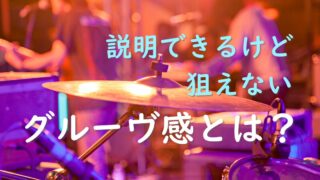

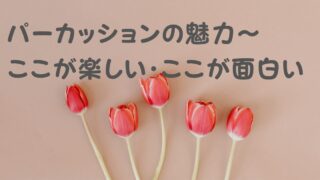
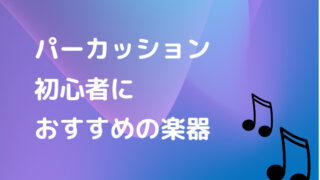
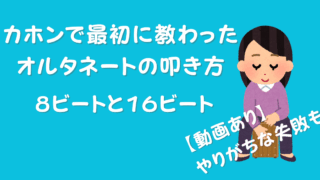

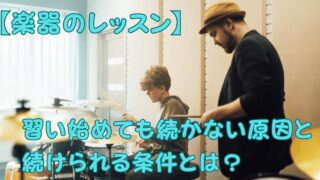




コメント