最近、カホンやジャンベ、コンガなどの打楽器をライブや動画で見かける機会が増え、「ちょっと叩いてみたいな」と興味を持つ方も多いのではないでしょうか。
でもいざ始めようとすると、「どれを選べばいいの?」「音楽経験がなくてもできる?」「家で叩いて大丈夫?」など、気になることや不安も出てきますよね。
この記事では、これから打楽器を始めてみたい方に向けて、初心者が感じやすい6つの疑問に答えながら、楽器選びのヒントや、始めるときのコツをやさしくご紹介します。
「打楽器って楽しそう!」という気持ちを大切に、一歩踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
楽器選び|どれを選べばいい?ドラムとの違いも解説

打楽器とひとくちに言っても、種類は本当にたくさんあります。
「パーカッションとドラム、どっちがおすすめ?」「初心者に向いているのはどれ?」と迷ってしまう方も多いと思います。
ここでは、まずパーカッションとドラムの違いから始めて、初心者に人気の楽器や、それぞれの特徴をわかりやすくご紹介します。
パーカッションとドラムの違い
まずは、パーカッションとドラムの違いから。
一般的に「ドラム」と言うと、ドラムセット(セットドラム)を指します。
これはバスドラム、スネアドラム、タム、シンバルなどが組み合わさった、複数の打楽器をひとりで演奏するスタイルです。

一方で「パーカッション」は、叩いたり振ったりこすったりして演奏する楽器全般を指す言葉です。
言葉の意味としては、ドラムもパーカッションに含まれます。
ただし、一般的に「パーカッション」と言う場合は、ドラム以外の楽器──コンガ、カホン、ジャンベ、タンバリン、シェイカーなどを指すことが多いです。
これから打楽器を始めたいという初心者の方には、「ドラムとパーカッションどっちがいい?」と迷われる方もいるかもしれません。
そう迷った場合、私は初心者が“すぐに楽しめる”のはドラムだと思います。
ドラムは非常に完成された楽器で、初心者でも叩けばそれなりの音をすぐに出すことができます。
いつも聴いている音楽で使われているような、なじみのあるリズムも、簡単なものであれば割とすぐに演奏できて楽しめます。
もちろん、上達してくると奥深くて挑戦しがいがあるし、バンドなどでも欠かせません。

「かっこいいリズムが叩けるといいな!」という感じで気軽に始めたい方には、ドラムがおすすめです。
ただ、ドラムとパーカッションで迷っているということは、パーカッションならではの魅力にも惹かれているということかと思います。
パーカッションの楽器は、それぞれがとてもユニークで、簡単にはいい音が出ないものもありますが、じっくり向き合っていくのはほんとに楽しいですよ。
ドラムにはない魅力がたくさんあります。
だからこそ、ぜひご自身の興味に合わせて、パーカッションの世界にも飛び込んでみてほしいです(*゚∀゚)
たとえばカホンは、持ち運びが簡単で、ドラムのようにリズムを支える役割もこなせる便利な楽器です。
バンドなどでドラムのように使いたい方には、カホンという選択肢になると思います。
またパーカッションは、ラテン音楽や民族音楽だけでなく、ポップス、ロック、ジャズなどさまざまなジャンルで活躍します。
複数の楽器を組み合わせて自分らしい演奏スタイルを作れるのも魅力だし、アコースティックなセッションでは、特に存在感を発揮します。
どっちも気になる、ということであれば「まずは片方を始めてみて、その後もう片方もやってみる」というのもありです。ぜひ気軽にはじめてみてください。
初心者におすすめの打楽器は?

初心者におすすめされることが多い、カホン、ジャンベ、コンガ、ボンゴについて簡単にご紹介します。
- カホン:
木箱型の楽器で、箱の上に椅子のように座って叩きます。
シンプルな構造ながら、叩き方によって豊かな表現が可能で、アコースティックな音楽にもよく合います。
また、ドラムのように演奏できるため、ジャンルを問わず使いやすいのも特徴です。
打面が木でできているため、初心者でも音が出しやすく、演奏が形になりやすい楽器と言えるでしょう。 - ジャンベ:
西アフリカ発祥の太鼓で、音量や表現力も豊か。ドラムサークルなどでも人気です。
民族音楽のイメージが強いですが、ポップスにも合う曲があり、バンド演奏で使われることもあります。
少し哀愁のある、長く響く音が特徴です。 - コンガ/ボンゴ:
もともとは、ラテン音楽で使われる皮張りの太鼓ですが、現在はラテンに限らず、ポップスなどさまざまなジャンルで広く使われています。
演奏の難易度はやや高めで、特にコンガで良い音を出せるようになるには時間がかかります。
(とはいえ、途中段階でも十分楽しむことはできます)
パーカッションを代表する楽器でもあり、その音と存在感には大きな魅力があります。
✅初心者におすすめの楽器と難易度は、下の記事でより詳しくまとめています。
興味のある方はぜひご覧ください。
✅コンガとジャンベの違いは、下の記事で解説しています。
✅コンガについては、下の記事で紹介しています。
✅ジャンベについては、下の記事で紹介しています。
✅カホンについては、下の記事でも紹介しています。
「珍しい楽器をやってみたい」人の選択肢
もしあなたが「他の人と違うことをしてみたい」「珍しい楽器に惹かれる」タイプなら、ユニークな打楽器が世界中にたくさんあります。
もしかしたら、すでに気になる楽器があって「これをやってみたい」と思っているかもしれませんね。
ここで紹介するのはほんの一例です。世界には、ここには書ききれないほど個性的な楽器があります。
- ウドゥ:
壺のような形の陶器楽器。指で叩いたり空気を鳴らしたりする独特の奏法が特徴です。
音が小さめなので家の中でも演奏しやすい。
しっとりした曲で効果音のように使うこともあります。 - パンデイロ:
ブラジル音楽で使われるタンバリンのような楽器。
伝統的にはサンバのリズムを演奏しますが、ドラムパターンも表現できます。
手数が多く、テクニカルな演奏が魅力です。 - ダラブッカ:
中東やトルコなどで演奏されるゴブレット型(ワイングラス形)の太鼓。
片手で軽快なリズムを刻みながら、指先で細かい装飾音を出すのが特徴。
独特の高く澄んだ音色とが魅力。美しい楽器が多いのも素敵なところです。 - タブラ:
インド古典音楽で使われる一対の小太鼓。左右で大きさが異なり、手や指を複雑に使って豊かな音階や独特の響きを生み出します。
インドの伝統的なリズムは奥深く洗練され、新しい表現も生まれています。
比較的音が小さく、家の中でもぎりぎり練習できるそうです。 - トーキングドラム:
西アフリカに伝わる砂時計型の太鼓。脇に抱えて叩きながら、紐を締めたり緩めたりして胴を締めることで音の高さを変えられます。まるで人の声のように抑揚をつけられることが名前の由来。
実際にこの楽器を手に入れると「こんにちは」「私の名前は○○です」と“しゃべる”ように演奏して遊びがち。

こうした楽器は演奏人口が少ないぶん、一度好きになると深く追求する人が多い印象です。
それぞれの楽器に専門の演奏家がいて、挑戦するなら近くに教えてくれる先生を見つけられるかがポイントかもしれません。
ただ、専門の演奏家でなくても、演奏にこうした楽器を取り入れているパーカッショニストもいるので、「ちょっと体験してみたい」という場合は、一般的なパーカッションを学ぶレッスンの中で、触れることが可能なこともあります。
(先生によるので、興味がある場合は最初に問い合わせてみてください)
ジャンルとの相性

打楽器(パーカッション)が活躍する音楽ジャンル
打楽器(パーカッション)というと、ラテンや民族音楽のイメージが強い方も多いかもしれません。
でも実は、ポップス、ロック、ジャズなど、あらゆるジャンルの音楽でさまざまな打楽器が使われています。
たとえば、ライブでよく見かけるカホンは、ポップスやロックでも活躍しています。
シェイカーやタンバリンなどの小物楽器と組み合わせて演奏されることも多いですね。
また、ジャズやポップスのバンドにコンガやボンゴが入ると、独特のグルーヴ感が生まれるのも魅力です。
もちろん、ラテン音楽にはコンガやボンゴが欠かせません。
アフリカンリズムに挑戦してみたいなら、まずはジャンベから始めるのがおすすめです。
サンバが好きな方には、スルド(大太鼓)、タンボリン(手で持つ小さな太鼓)、カイシャ(スネアドラム)などのブラジル楽器が本格的ですが、バンド演奏ではカホンやコンガなど、一般的な打楽器で演奏されることも多いです。
フラメンコに興味があるなら、やっぱりカホンですね。
カホンは、今やフラメンコの伴奏に欠かせない存在です。
足でリズムを刻むダンサーとの即興的な掛け合いはとても迫力があります。
そして、最近人気が高まっているのがドラムサークル。
特定の曲や楽譜はなく、参加者が自由に太鼓を叩いて、リズムで“対話”するセッションです。
通常はファシリテーター(リーダー)がいて、進行をガイドしてくれます。
初めてでも簡単なパターンを真似するだけで、音楽の一体感を味わえるのが魅力です。
自分に興味に合った先生やサークルを選ぶ
このように、打楽器はさまざまなジャンルで楽しむことができますが、始めるときは「自分がどんなことをやりたいか」を考えることがとても大切です。
そして、そのジャンルに詳しい先生やサークルを選ぶのがおすすめです。
(違うところに行くと、「思ってたのと全然違う」ということに…)
ざっくり分けるなら、
「ポップスの曲を演奏したいのか」
「ジャズをやってみたいのか?」
「ラテンやアフリカのリズムに興味があるのか?」
「バンドで演奏したいのか、民族音楽をやりたいのか」
といった視点で考えてみてください。
教室のホームページなどには、先生がどいういったジャンルで活動しているか書かれているので、参考にするといいと思います。
もし、自分の興味にピッタリのジャンルで先生がみつかれば、その先生に教わるのが一番のおすすめです。
ただ近くに、ぴったりの先生が見つからない場合も多いかもしれません。
その場合も始められないということはありません。
プロのパーカッショニストは、大体どのジャンルでも演奏できるので、近いジャンルで”何となくよさそうだな”と感じる先生や教室があったら、まずそこで初めてみてはどうでしょう。
こんな曲がやりたいと伝えて、演奏を教わることもできるし、あまり知らなかった音楽を知るのも楽しいものです。

「そこまで考えてない」「ジャンルとかよくわからないけど、コンガとかボンゴとかがやってみたい」「何となくカホン面白そう」という感じなら、とりあえずスクールのパーカッション教室で体験してみるのがおすすめです。
限定されたジャンルに興味がある場合は、ピンポイントで探すこともできます。
- バンドでカホンを演奏したい場合は、ドラマーがレッスンをしている場合があります。
- アフリカンリズムに興味があるなら、ジャンベやアフリカ太鼓が専門の先生から学ぶと、より深く楽しめます。
- ラテン系なら、地域のラテンサークルを探すと出会いがあるかもしれません。
- 本格的にブラジル楽器を演奏したいなら、サンバチームに入るという手も。体験レッスンを実施していることも多いと思います。
- フラメンコのカホンをやりたい場合は、フラメンコのリズムは特殊なので、フラメンコ専門の先生からでないと、学べないと思います。
そういった先生は、ダンス教室の伴奏をしていることも多く、上達したらダンサーとの共演のチャンスも得られるかもしれません。 - ドラムサークルに参加したいなら、「地域名+ドラムサークル」などで検索して、通いやすい場所を探してみてください。
ぜひ、ご自身がどんなジャンルに惹かれるかをどんなことをしたいかをヒントに、学ぶ場所や先生を選んでみてください。
始め方に関する疑問|スクール?独学?まず何する?

打楽器に興味はあるけれど、実際に始めようとすると「何から始めればいいの?」「いきなり楽器を買って大丈夫?」「やっぱりスクールに行くべき?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、初めて打楽器に触れる方が安心して始められるためのヒントをお伝えします。
最初の一歩は?|まずは“触れてみる”
打楽器を始めるとき、いきなり楽器を買ったり、YouTubeで独学を始めたりする前に、「まずプロと一緒に、実際に叩いてみる」ことを、ぜひ体験していただきたいです。
というのは、打楽器は実は意外と音が大きく、家や近所の公園で簡単に叩くことは難しいです。
また、打楽器は叩くだけで簡単そうに思えるかもしれないけど、その楽器本来の音はすぐに出せるものではありません。
ですから、興味ある楽器を買ってきて自分で叩いてみる、というのでは、その楽器の面白さはなかなかわからないのです。
たぶん「ふーん」「こんな感じなんだ…」という、もやっとした感じになるかも?
また、動画で見て真似してみても、一度もやったことがない状態では、本来どのくらいの音が鳴るのか、叩く時の勢いはどのくらいか、などはわからないと思います。
ですから、最初はぜひプロに教わって、プロの演奏を間近にみて、叩き方を教わることのできる場所に行ってみてください。
音楽スクールやサークルでは、体験レッスンやワークショップなども用意されています。
一度参加してみると、「自分に合う・合わない」もわかるし、「近くで聴くとこんなに迫力あるんだ!」と感動するかもしれませんよ。
独学でもできる?スクールに通うべき?
打楽器は、独学でも始めやすいように見えるかもしれません。
実際、YouTubeや本などの教材もたくさんあります。
ただ、打楽器を楽しむには、独学ではなく、レッスンを受けてプロから習うことをおすすめします。
ピアノやバイオリンを始めるときに独学でやってみようと思う人はあまりいないですよね?
それと同じです。
でも自分は独学でやりたい、という方は、最初だけでもレッスンを受けて、実際にプロが叩くとどんな音が鳴るのか、リズムの基本や叩き方の基本などをひととおり教わってから、自分で練習してみてはどうでしょうか。
スクールに通わなくても、単発のワークショップやグループレッスンなど、気軽に参加できる機会もありますので、「スクールを続けることができるかわからない…」という方も、まずは気軽に体験してみていただけるといいと思います。
楽器の購入について
楽器は、最初から買わなくても大丈夫です。(むしろ買わない方がいい)
大体のスクールやサークルでは、楽器を貸してもらえるので、楽器がなくても体験できます。
(経験者対象のワークショップなどでは、自分の楽器を持って行く必要のある場合はあるかもしれません)
一度体験してみて、レッスンを受けてみよう、続けたい、と思ってから購入してください。
レッスンでもほとんどの教室にはレンタルの楽器があります。
教室が決まったら、どの楽器を買えばいいか相談してみるのもおすすめです。
レッスンを何回か受けてから購入する人もいるし、コンガのようになかなか自分では持てないような楽器もあります。
打楽器にかかる費用は?(楽器代・レッスン代など)
費用は、楽器の種類や始め方によって大きく変わりますが、ざっくりとした目安をまとめておきます:
楽器代
価格帯は幅広く、比較的低価格のものから高価なものまでさまざまです。
「続くかわからないから出来るだけ安く始めたい」、という人もいるし、「どうせ買うなら最初からある程度いいものを…」と思う人もいます。
エントリーモデル(初心者向け)でもいいけど、人によっては、続けるうちに物足りなくなって買い替える場合も。
ここでは、ざっくりとした初心者むき価格帯のイメージをまとめました。(ほんとにざっくりなので、参考程度に…。2025年9月時点)
- カホン:1万円台後半~3万円
※ほとんどは2万円台。
1万円以下の安すぎるものは、おもちゃだと思った方がいいです。 - ジャンベ:1.5万〜3万円台
※サイズによる。メーカーのものと、アフリカなど現地で作られたものがあります - ボンゴ:2万円〜
- シェイカー:数百円~数千円
※シェイカーはおもちゃみたいなものの中にも、意外といいものがある場合も。 - タンバリン:1,000円台〜
※楽器として本格的なものは5000円以上~
最初からコンガを買うことはほぼないと思います。
楽器の購入は、先生が決まったら相談できるので、慌てて検討せず「このくらいかかるんだ」と参考程度にしてください。
それぞれの楽器についてまとめた記事を以下に紹介します。
興味のある楽器があったら、ぜひ参考にしてください。
■カホンの選び方、おすすめカホンの記事
■ボンゴの選び方、おすすめボンゴの記事
■タンバリン、カホン用シンバルの記事
レッスン・体験の費用
これも、そのスクールや団体によるので、ほんとに参考程度です。
体験は無料のことも多いと思います。
- 体験レッスン(30分〜1時間):無料〜2,000円程度
- 月謝制の教室:月4,000円〜8,000円前後(個人/グループで変動)
- 単発ワークショップ:2,000円〜5,000円程度
※本格的なサンバやアフリカ系楽器などでは、団体所属費・衣装代などが必要な場合もあります。
演奏スタイル・楽しみ方|ひとりでも?アンサンブルでも?

「打楽器って、ひとりで叩いても楽しいの?」「一緒に演奏する人はいないんだけど…」
そんなふうに思っている方も多いかもしれません。
でも実は、打楽器にはひとりでじっくり楽しむこともできるし、誰かと一緒に演奏するのはもちろん楽しい。
ここでは、打楽器のさまざまな楽しみ方をご紹介します。
ひとりでも楽しめる打楽器の魅力
打楽器は、ひとりでも十分楽しめます。
むしろ最初は、自分の好きな曲に合わせて叩いたり、リズムパターンを練習したりなど、ひとりで練習することの方が多いです。
好きな曲の音源に合わせて練習するのは、とても楽しくて私も大好きです。
ひとりで叩いていると、自分のリズムに集中できるし、ちょっと疲れた日や気分転換したいときに、気持ちがリフレッシュされて頭がすっきりします。
もちろん、ひとり練習は上達に必要なことでもあります。
自分の手の動きや音のバランスをじっくり確認しながら、少しずつできることが増えていく感覚は、打楽器ならではの楽しさです。
アンサンブルって難しそう?まずは簡単なリズムから
少し叩けるようになったら、誰かと一緒に演奏したくなるかもしれません。
打楽器のアンサンブルは“簡単なパターンを重ねるだけ”でも十分楽しい。
他の楽器を演奏する家族や友人に「一緒にやってみない?」と声をかけてみてはどうでしょう。
近くに、ピアノ、ギター、ベースやヴォーカルなどをやっている人はいませんか?
誰かと音を合わせることで、自分ひとりでは味わえない高揚感やグルーヴ感が生まれてほんとに楽しいし、やってみると、「意外と音楽になった」「なかなか難しいな~」などいろんな感覚が生まれると思います。
誰かと一緒にやることが、上達への近道といいます。
機会があったら是非挑戦をしてみてください。

私は初心者のころ、ピアノをやっている友人に声をかけて、組んで演奏したのが初めての経験でした。友人が通っていたスクールのイベントに、2人で参加したのも楽しかったです。
また、楽器練習が黙認されている大きな公園に行ったら、ギターをやってるおじさまたちがきて、セッションになったのも楽しい思い出です。
路上ライブやセッションに参加できる?
ある程度叩けるようになってくると、「人前で演奏してみたい」と思う方も出てくるかもしれません。
特にカホンは持ち運びしやすく、セッティングが簡単なので、路上ライブやアコースティックイベントなどでも活躍しやすい楽器です。
地元のイベントにも参加しやすいのではないでしょうか。
また、自分でライブを開催したり参加したりするのは敷居が高いかもしれないけど、スクールやサークルによっては初心者でも気軽に参加できるライブイベントを開催しているところもあります。
人前で演奏して聴いてもらうのは、緊張するけどそこが演奏のだいご味でもあります。
思いがけず褒められたり、打楽器の場合めずらしいので楽器自体に興味をもってもらったり、とても良い機会になりますよ。
自宅で叩ける?騒音は大丈夫?
打楽器は、意外と音が大きい。
ほとんどのパーカッションは、普通の住宅環境ではそのまま叩くのは難しいです。
アパートに住んでいた時は、私はタンバリンやシェイカーでも部屋で練習するのは気が引けてできませんでした。
戸建てや防音のしっかりしたマンションなら、楽器をミュートすれば練習できる場合もあるかもしれませんが、とにかく打楽器は練習場所に苦労するというのが本当のところです。
詳しくはこちらの記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください👇
練習方法への疑問

リズム感がなくても大丈夫?感覚を育てるコツ
「リズム感がなくても大丈夫?」「私はリズム感がないから無理」
これは一番多い不安かもしれません。
でも実は、リズム感は“感覚”として育てていくものです。
まずは、自分の中で「一定のテンポを感じる」練習から。
手拍子をしながら歩いてみたり、音楽に合わせて軽く身体を動かしてみたり──そういったシンプルな感覚からリズムは育っていきます。
そして、先生について打楽器を練習するうちに、リズムを感じる力は育って行きます。
私も、自分ではリズムぴったりのつもりが、先生からみると「ずれてるよ」ということもよくありました。
地道なリズムトレーニングをしたり、いろいろな曲で経験をするうちに、自分でも気づかないうちにリズム感がよくなってきます。
だからこそ、「リズム感がないからやめておこう」と思わずに、まずはぜひ試してみてほしいです。
リズム感については、下の記事の最後のところ「(おまけ)リズム感のない人はほとんどいないらしい」の中でも書いています。
メトロノームや音源
打楽器の練習では、メトロノームや好きな曲の音源を活用は一番よく使うものかもしれません。
メトロノームは最初から買う必要はなく、スマホの無料アプリで十分です。
また、音源もスマホからスピーカーに出力して使えるし、もし曲が早すぎて手が追い付かない場合は、テンポを落として再生するアプリもあるので、速い曲でも結構練習できます。
詳しくは、下の記事で紹介しています。
大人からでもできる?という不安|経験ゼロでも大丈夫?
「子どもの頃に音楽経験がなかった」「楽譜が読めない」「リズム感に自信がない」──
そう感じている大人の方でも、打楽器は安心して始められる楽器です。
まずピアノや弦楽器のように音程がないので、「楽譜が読めない」ことのネックはかなり低くなります。
最初は簡単なリズムを繰り返すだけでも、十分に「音楽している」実感が得られ、そこから少しずつ難易度を上げて言って、いつの間にか「こんなことが出来るようになった!」という喜びが感じられることも。
また、打楽器には正解がひとつではないという魅力があります。
たとえば、「自分の好きなリズムで、好きな曲に合わせて叩いてみる」──それだけでも、十分に楽しい時間になります。
実際パーカッションは”これが正しい”という叩き方がない楽器も多く、プロでも人によって違うやり方をしていることも結構あると思います。
基本がしっかりしているに越したことはありませんが、「こう叩かないとダメ」というルールばかりではないのが打楽器の自由なところです。
年齢を重ねると、「今さら始めても遅いのでは?」と思ってしまうこともあるかもしれません。
でも、実際には40代、50代、60代から始めている方もたくさんいます。
むしろ大人の方が、表現力や音楽の深みを味わいながら、長く楽しむことができる趣味になることも。

私も50代になってから始めて、ずっとハマりっぱなしです。
また、パーカッションは楽器の種類が多く、いろんな楽器に挑戦できるし、同時に複数の楽器で演奏することもでき、飽きっぽい人にもおすすめです。
大切なのは、年齢や経験ではなく、「楽しんでみたい」という気持ちです。
レッスンも、「趣味としてマイペースに楽しみたい」というスタンスで参加している人が多いので、肩の力を抜いて、自分のペースで始めてみてくださいね。
まとめ
打楽器は、初めてでもすぐに音を出せて、誰でも音楽の楽しさを感じやすい楽器です。
その一方で、叩くだけに見えて、実はとても奥が深く、自分のペースでじっくり楽しむこともできます。
「気になるな」「ちょっとやってみたいかも」と思ったら、まずは体験レッスンやワークショップなど、ぜひ気軽に触れてみてください。
この記事が、打楽器に興味を持った方の参考になれば嬉しいです。
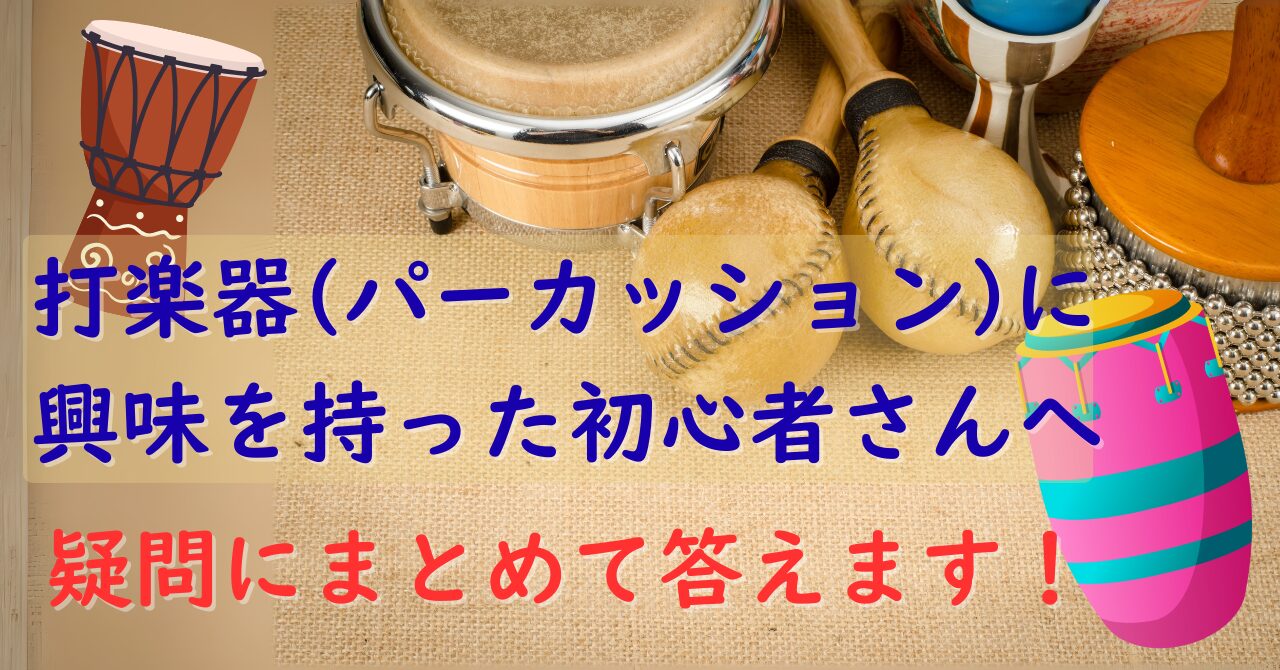
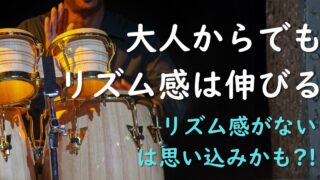


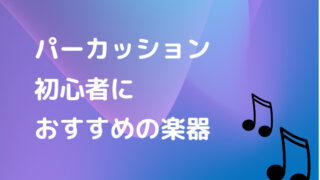







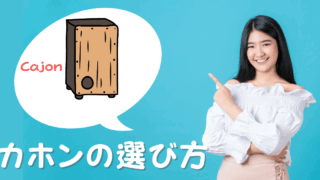



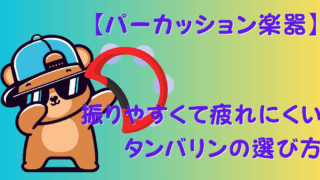
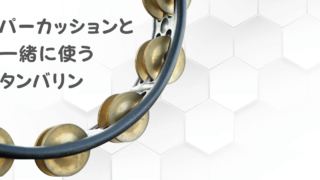



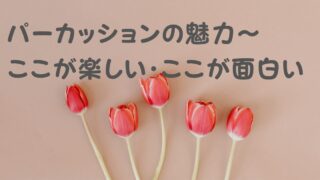



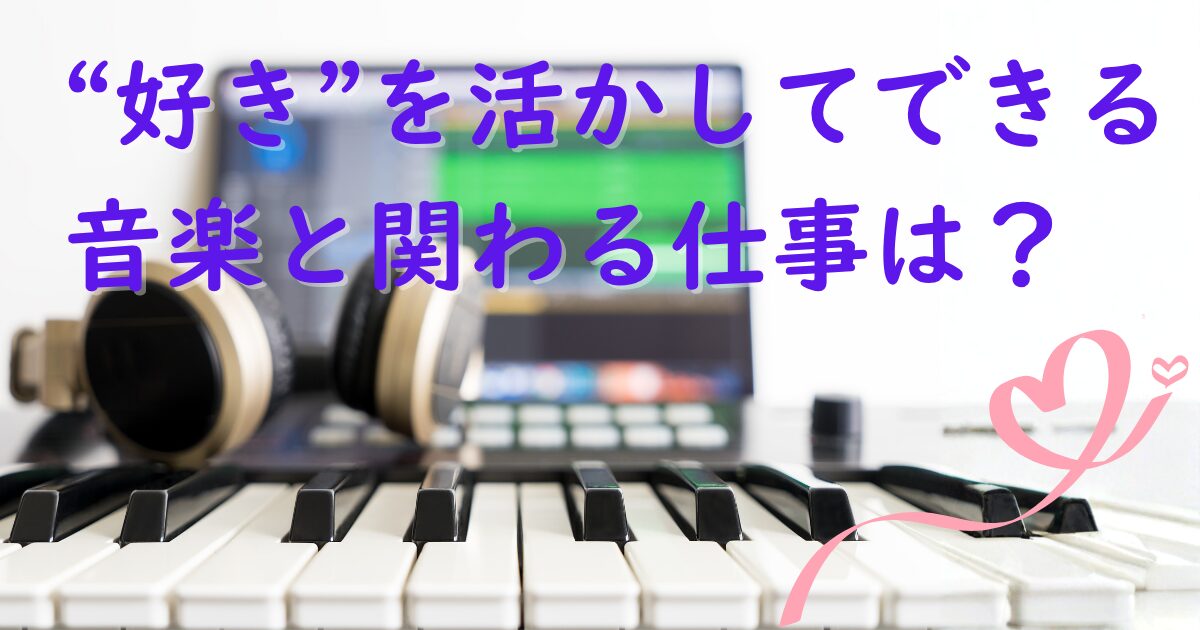
コメント